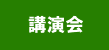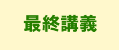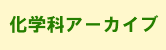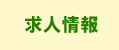2001.11.21 立花先生・島先生講演会
化学史入門
講師: 立花 太郎 お茶の水女子大学 名誉教授

まず、昨年に引き続いて今年もノーベル化学賞を日本の野依良治名大教授が受賞されたこと。昨年の白川英樹氏の研究の源流は、東大鮫島研で行われた“有機化合物の導電性”という日本の研究であり、その研究者の一人井口洋夫氏は今年の文化勲章を受章されたことを述べられた。
§1 化学のアイデンティティー
化学の柱は分析・合成・構造決定であるが、現在はそのいずれもが、物理的方法あるいは量子力学の計算に基づいている。
1985年のノーベル化学賞の受賞者の一人は数学者であり、New York Timesは“chemistry is losing identity”と書いた。化学のアイデンティティーはどこにあるのか?それを探るには歴史を知る必要がある。
§2 化学者による化学者のための化学史
1799年にJ. F. Gmelin(独)は「Geschichte der Chemie」を、1970年にPartington(英)は4巻から成る『化学史』を著している。日本では、岡山の第六高等学校の山岡望氏が『化学史伝』(1922年、1968年)を書かれた。山岡氏は日本の化学教育に尽くされ、玉虫文一氏と共に第1回の日本化学会化学教育賞を受けた。
立花先生が学ばれた時代には、東大では化学史の講義は物理化学の講義の中で十数時間行われていた。
§3 伝統的化学史への批判
化学者の意識で書かれた伝統的化学史は、現在主義の史観、勝利者主義の史観に傾いているという指摘が、1966年Thackrayによりなされた。柏木肇(名大)はThackrayの論文を日本に紹介した。1974年には、日本に「化学史研究会」(後に「化学史学会」) が創立された。
§4 一般科学史の主題とアプローチ
一般科学史は、科学の発展について形而上学的要因と社会学的要因の両面から考察し記述されてきた。
B. M. Hessen(露)は1931年にマルクス主義の立場から『ニュートン力学の形成』を、A. Koyre(佛・米)は“見えない理想の世界が現実の裏側にある”というプラトンの哲学の流れをくみ、“自然界の事象は、全て数学で記述できる”というガリレオの考えの下に、1939年に『ガリレオ研究』を著した。
T. Kuhnは16世紀から17世紀にかけて知の世界に変動が起こり、従前のアリストテレスの力学とニュートンの力学はまったく違うこと、つまり科学革命が起こったと考えた。パラダイムの変換は不連続的に変化するという考えの下に、1962年に『科学革命の構造』を著した。
§5 一般科学史の各論としての化学史
一般科学史の各論としての化学史という立場で書かれた先駆的な『化学史』は1930年にH. Metzger女史によって発表された。
§6 化学史叙述の新段階(20世紀後半期)
20世紀後半期には、文献に挙げられているように、総合的および専門的視野からの化学史が発表されたが、C. A. Russell(英)は、天才の伝記だけでなく、庶民の科学に対する態度を理解する上では、三流の化学者も伝記の対象となると指摘した。
日本の知の革命は、夏目漱石、森鴎外において文学的創造に結実した。鴎外の史伝『渋江抽斎』は江戸時代の三流の学者を描いた、生涯の傑作とされている。その人と時代が精細に描かれており、その叙述の手法は理系の者には興味深い作品である。
キュリー夫人伝は、娘のEveの作(1938年)以外に、英国人Reid(1974年)Giroud(1981年)、Quinn(1955年)のものがあるが、Eveの著作が聖女像に描かれているのに対して、他の著者のものは、スキャンダルも含め、生き生きとした人間像が描かれているとするフェミニズム科学史も開拓されつつある。
§7 科(化)学史から見た人間文化および社会的な諸問題
科学は人間の創造的活動の一つであり、人間文化は、“人文”と“科学”の提携によって発展していく。
Sartonは“人文系の知識人の考える文化”と“科学者の考える文化”の二つの文化を“科学史により橋を架けることで新しい“ヒューマニズム”が生まれると考えた。 因みに、お茶の水女子大学の人間文化研究科の設立に理学部も参加した背景には、この考えがこめられていた。
また、夏目漱石はロンドン留学中の1901年5月に、物理化学者池田菊苗に出会うことで触発され、『文学論』を著したことも述べられた。
********************************************************
2. (昭和52年卒 青山聖子さんによるまとめ)
●立花先生ご講演要旨
化学の主な守備範囲は「分析」「合成」「構造決定」であり、これらは19世紀から可能であったが、20世紀に手法が大きく変わった。分析と構造決定においては物理学的手法が、合成においては量子力学計算による予測が用いられ、物質の発見と合成には分子生物学や医学の研究者も加わるようになった。こうした変化により、現代は化学のidentityが問われる時代となっており、それは時代とともに変化して今日に至ったわけだから、いまこそ、化学史を振り返ることは意義深い。
1799年のGmelin以来、化学史は何通りも書かれてきたが、伝統的化学史は化学の世界の中にしか目を向けておらず、科学史家からは批判を受けてきた。その批判とは、化学史も科学史全体の流れの中で捉えられるべきものであり、さらに、科学は自律的に発展したものではなく、哲学、神学、思想といった形而上学的要因と、経済、教育といった社会学的要因を考慮する必要があるという指摘である。
このような視点に立つ最初の化学史は、Metzger女史が1930年に著し、その後の化学史は、化学を内側と外側から捉えるものへと変貌した。これらを通じて、物理学におけるコペルニクス(天動説)→ガリレオ(地動説)→ニュートン(力学のまとめ上げ)の図式で示される力学の変革に相当する化学の流れが浮かび上がる。それは、Lavoisierによる、燃焼のフロギストン説から酸素説への転換であり、そこには形而上学的要因や社会学的要因が働いていた。
科(化)学史や学者の伝記は、当時の社会の科学への態度を映すものとも言える。たとえば、明治の代表的知識人、夏目漱石は理系の素質があり、物理化学者の池田菊苗とも親交があったし、森鴎外は医者でもあった。彼らの作品には、当時の知識人の科学観が現れており、興味深い。