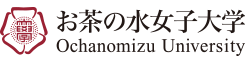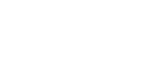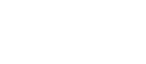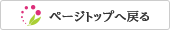ページの本文です。
近藤 るみ(こんどうるみ)
2021年7月7日更新
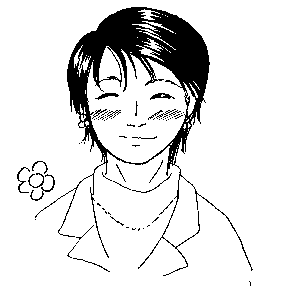
近藤 るみ (こんどう るみ)
分子進化学、進化遺伝学、実験集団遺伝学
“生命”って不思議...どんな仕組みになっているのだろう。多種多様な生物はどうやって生じたのだろう。この様なごく自然な興味から生物学の世界に引き込まれていきました。そして本学に入り、講義・実習と研究生活などを通して新しい発見がなされていく喜びを垣間見ることができました。すると世界中の研究者が一つの巨大なジグゾーパズルに取り組んでいる様子が見えてきました。長い年月をかけて幾つもの研究の成果が積み重なって、少しずつ、そこに描かれている絵が現れていきます。私たち自身が完成された姿をみることはできませんが、私もその絵に自分のピースをはめ込んでみたいと思いました。
皆さんも一緒にこの楽しみを味わってみませんか。
研究紹介
所属 |
基幹研究院 自然科学系 准教授 |
|---|---|
担当大学院(教育院),学部 |
博士後期(博士)課程 ライフサイエンス専攻 生命科学領域 ライフサイエンス専攻 遺伝カウンセリング領域(兼担) 博士前期(修士)課程 ライフサイエンス専攻 生命科学コース ライフサイエンス専攻 遺伝カウンセリングコース(兼担) 理学部生物学科 |
主な担当授業科目(学部) |
基礎遺伝学、進化遺伝学、基礎遺伝学実習、生物学実習I・II、 生命と色・音・香、基礎生物学B、特別研究I・II、生物学演習I・II |
主な担当授業科目(大学院) |
集団遺伝学、集団遺伝学演習、集団遺伝学特論、分子進化学 |
専門分野 |
分子進化学、進化遺伝学、実験集団遺伝学 |
所属学会等 |
日本遺伝学会、日本分子生物学会、日本ショウジョウバエ研究会 The Society for Molecular Biology and Evolution |
研究室 |
理学部1号館 518, 513, 514, 517号室 |
|
|
kondo.rumi |
主な研究課題とその紹介
当研究室では、遺伝子からゲノム、細胞、個体、集団、行動、進化といったあらゆるレベルの研究の最先端でモデル生物として活躍しているショウジョウバエを研究材料に用いています。近縁種の野生型系統や遺伝子組換え系統を目的に応じて作成して、表現型多様性や進化の遺伝的基盤を明らかにする研究を行っています。
- 嗅覚・味覚の判断行動の適応進化
生物は、外界の匂いや味を判断材料として生きています。多くの昆虫は、餌とする生物(宿主)が種間で違えることで棲み分けており、成虫は幼虫が好む餌を選んで産卵する宿主特異性を示します。キイロショウジョウバエ(Drosophila melanogaster)の近縁種には、キイロショウジョウバエと同様に様々な果実を宿主とする広食性のオナジショウジョウバエ(D. simulans)とノニの果実のみを宿主とする狭食性のセイシェルショウジョウバエ(D. sechellia)が存在します。本研究室では、セイシェルショウジョウバエが、他のショウジョウバエにとって有毒なノニ果実の成分に耐性があり、ノニ果実が発する匂いに強く誘引され、味を確認して産卵する宿主特異性を示すことに着目しています。宿主に含まれる何らかの化学物質を識別して選択する行動がDNAによって決まっており、進化の過程で変化し、また維持されているようです。そのような判断行動の適応進化の遺伝的基盤を明らかにすることを目指しています。
- 転移因子の拡散と維持機構
全ての生物のゲノムには、転移因子という、ゲノム上の位置を移動して挿入(転移)またはそのコピーを増やすDNA配列が多数存在します。転移因子は、遺伝子の変異原となり、ゲノム構造の多様性にも大きな影響を与えています。一方、真核生物はそれらの転移を抑えるための防御機構を獲得しています。本研究室では、最近ヨーロッパでキイロショウジョウバエのゲノムからオナジショウジョウバエのゲノムに水平伝播で侵入した転移因子であるP因子に着目し、日本のオナジショウジョウバエの地域集団へのP因子の侵入と拡散を調査して、P因子の転移に対する防御機構の獲得とP 因子の維持機構を明らかにする研究を行っています。
- ショウジョウバエをモデルに用いた健康維持に関する研究
全ての生物は共通の祖先から進化しました。そのため、系統的に異なる生物間でも共通する生命現象が保存されています。ショウジョウバエを用いた研究によって、ヒトを含む多くの生物が共有する生命現象が明らかにされています。また、キイロショウジョウバエとヒトのゲノムの比較により、ヒトの疾患に関わる遺伝子の約61%がショウジョウバエにもあることがわかっています。また、ヒトとハエの分子メカニズムが保存しており、ヒトの疾患に効果のある薬剤がショウジョウバエにも同様の効果がある例が多く知られています。本研究室では、ショウジョウバエの系統間の体質の違いに着目し、与える環境が個体の体調(行動、寿命、代謝)に与える影響を明らかにすることにより、ヒトの健康維持に役立てたいと考えています。
主な研究論文
- Expression divergence of chemosensory genes between Drosophila sechellia and its sibling species and its implication for host shift. Genome Biol. Evol. 7(10):2843-2858.(2015)
- Transcriptional profiling of adult Drosophila antennae by high-throughput sequencing. Zoological Studies 52:42. (2013)
- Seasonal changes in the long-distance linkage disequilibrium in Drosophila melanogaster. Heredity 101(1):26-32. (2010)
- A new test for detecting ongoing selection. Genetica;133(3):321-34. (2008)
- Interlocus nonrandom association of polymorphisms in Drosophila chemoreceptor genes. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 101(39):14156-1416. (2004)
- Evolutionary analysis of putative olfactory receptor genes of medaka fish, Oryzias latipes. Gene 231:137-145. (1999)
- Use of SV40 to immunize against hepatitis B surface antigen: implications for use of SV40 for gene transduction and its use as an immunizing agent. Gene Therapy. 4:219-225 (1997)
- Recent origin of human revealed by complete sequence of hominoid mitochondrial DNA. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 92:532-536 (1995)
- Peopling of the Americas, founded by four major lineages of mitochondrial DNA. Mol. Biol. Evol. 10:23-47(1993)
- Evoltion of hominoid mitochondrial DNA with special reference to the silent substitution rate over the genome. J. Mol. Evol. 36:517-531 (1993)
- Man's place in hominoidea revealed by mitochondrial DNA genealogy. J. Mol. Evol. 35:32-45 (1992)
- Further observation of paternal transmission of Drosophila mitochondrial DNA by PCR selective amplification method. Genet. Res. Camb. 59:81-84 (1992)
- Incomplete maternal transmission of mitochondrial DNA in Drosophila. Genetics,126:657-663(1990)
関連リンク / Related Links
»研究者情報-近藤るみ (新しいウインドウが開き、本サイトを離れます)