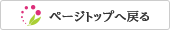化学科講演会の記録
2026年1月14日更新
2026年
● 2026.01.26 佐藤 縁 先生 講演会
日時: 2026年01月26日(月)16:40〜18:10
場所: 理学部1号館4階 化学第1講義室(421室)
講師: 佐藤 縁 先生
(国立研究開発法人産業技術総合研究所 省エネルギー技術研究部門 副研究部門長)
テーマ: 液体に電気を貯める:レドックスフロー電池のご紹介
要旨:
こちらからご覧ください。
● 2026.01.23 内藤 昌信 先生 講演会
日時: 2026年01月23日(金)15:30〜16:30
場所: 共通講義棟1号館404室
講師: 内藤 昌信 先生
(国立研究開発法人 物質・材料研究機構(NIMS) 高分子・バイオ材料研究センター 副センター長)
テーマ: ポリマーインフォマティクス最前線 〜高分子データを作る、貯める、活用する〜
要旨: サーキュラーエコノミーの実現に向け、データ駆動型高分子開発が加速しています。本発表では、自律実験システムや質量分析AI「ポリマーシークエンサー」による高品質データの生成(作る)、NIMSのデータ基盤への蓄積(貯める)について概説します。さらに、生成AIを用いた透明耐熱樹脂の開発や、選好学習による海洋分解性評価などの最新事例(活用する)を紹介し、マテリアルズ・インフォマティクスが拓く材料研究の未来を議論します。
● 2026.01.16 小田 玲子 先生 講演会
日時: 2026年01月16日(金)15:00〜16:30
場所: 人間文化創成科学研究科棟604室
講師: 小田 玲子 先生
(東北大学原子分子材料科学高等研究機構(AIMR)主任研究者、フランス国立科学研究センター(CNRS)第1級研究部長)
テーマ: Mesoscopic and hierarchical « chiral » objects to measure chirality
要旨: Chirality can be transmitted across various media and size scales, from spinning elementary particles and chiral molecules to mesoscopic and macroscopic structures through electromagnetic fields or emergent spin structures. The mechanisms underlying the transmission of chiral information, which can manifest in intra- and inter-atomic/molecular interactions, are highly complex and continue to fascinate scientists. When investigating systems spanning a wide range of sizes, hierarchical nanostructures based on molecular assemblies offer promising solutions to bridge the gap that is challenging to address using both top-down and bottom-up approaches. For several decades, we have developed helical nanostructures with controlled sizes ranging from 10 to 100 nm and defined handedness. These structures have shown significant potential not only as fundamentally intriguing objects with unique properties but also as helical platforms capable of transmitting chiral information between small and large scales, including electrons, atoms, molecules, large polymers, and even nanoparticles. Through these interactions, we have demonstrated exciting examples of their applications in chiral induction, amplification, crystallization, reactions, and chiral recognition. This discussion will explore how chiral components expressing chirality at various hierarchical scales can interact with each other, leading to either the enhancement or attenuation of chirality within chiral matrices. Particular attention will be given to the interplay between order and disorder and how it influences the expression of hierarchical chirality in diverse organic and inorganic chiral systems. This expressed chirality can be evaluated using various measurable parameters, such as morphological characteristics, chiroptical signals, reactivity, and recognition efficiency.
2025年
● 2025.11.13 Lennart Brewitz 博士 講演会
日時: 2025年11月13日(木)13:30〜14:30
場所: 理学部1号館4階 化学第1講義室(421室)
講師: Lennart Brewitz 博士
(Assistant Professor, Department of Chemical Biology, Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Warsaw (Poland))
テーマ: Alkynes and lactams are useful warheads for covalent inhibition of the SARS-CoV-2 main protease
要旨: Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland. lennart.brewitz@ichf.edu.pl The SARS-CoV-2 main protease (Mpro) is a nucleophilic cysteine enzyme which employs a catalytic dyad (i.e., His41 and Cys145) to catalyze hydrolysis of the viral polyproteins. Mpro catalysis is essential during viral replication; thus, Mpro is an attractive drug target, with multiple small-molecule Mpro inhibitors being approved for COVID-19 treatment, including nirmatrelvir and ensitrelvir.1-2 Nirmatrelvir inhibits via reversible covalent reaction of its electrophilic nitrile with the nucleophilic thiolate of Mpro (Cys145), while ensitrelvir inhibits by binding non-covalently at the Mpro active site.1,2 However, improved Mpro inhibitors are needed to overcome limitations associated with the clinical use of nirmatrelvir and ensitrelvir.3 We investigated the potential of penicillins for inhibition of Mpro due to their excellent safety profile. Mass spectrometry-based assays and crystallographic analysis revealed that penicillin sulfone derivatives can inhibit Mpro via covalent reaction of their β-lactam group with Cys145.4 Subsequently, we showed that the addition of a methoxy-substituent at the penicillin C6 position can alter the mechanism by which the penicillin derivatives inhibit Mpro.5 We also showed the potential of γ-lactams, which are substantially less electrophilic than β-lactams, for covalent Mpro inhibition.6 As a second line of investigation, we aimed at developing small-molecule Mpro inhibitors which employ alkynes as isoelectronic, but less electrophilic groups than nitriles for covalent reaction with Mpro. Importantly, we showed that alkyne derivatives of nirmatrelvir are potent Mpro inhibitors, which, unlike nirmatrelvir, react irreversibly with Cys145.7 The nirmatrelvir alkyne derivatives are of interest from drug development perspectives, because of the relatively weak electrophilicity of the alkyne group compared to other electrophiles commonly used for covalent reaction with Cys145, which may disfavor off-target reactivity. The combined results highlight the utility of lactams and alkynes as warheads for development of covalently reacting Mpro inhibitors and, by implication, inhibitors of nucleophilic cysteine enzymes other than Mpro. References [1] D. R. Owen et al. Science, 2021, 374, 1586. [2] Y. Unoh et al. J. Med. Chem. 2022, 65, 6499. [3] C. M. N. Allerton et al. J. Med. Chem. 2024, 67, 13550. [4] T. R. Malla, L. Brewitz, et al. J. Med. Chem. 2022, 65, 7682. [5] D.-G. Muntean et al. RSC. Med. Chem. https://doi.org/10.1039/D5MD00789E. [6] Gayatri et al. Chem. Sci. 2024, 15, 7667. [7] L. Brewitz, L. Dumjahn, Y. Zhao et al. J. Med. Chem. 2023, 66, 2663.
● 2025.11.5 市川 早紀 先生 講演会
日時: 2025年11月5日(水)10:30〜
場所: 理学部1号館1階 セミナー室(126室)
講師: 市川 早紀 先生
(Assistant Professor, Department of Molecular Medicine, Cornell University)
テーマ: Natural recognition motifs for the E3 ligase adapter cereblon
要旨: Understanding the biology of drug target proteins is essential to enhance drug discovery efforts and mechanistic studies. The clinical drug thalidomide is recognized by a conserved binding domain on the E3 ligase adapter cereblon (CRBN), resulting in lifesaving anti-cancer treatments or horrific teratogenicity. However, despite the growing use of CRBN in the lab and clinic, the mechanisms CRBN uses to recognize protein substrates have escaped definition for decades. E3 ligase complexes select proteins for degradation by recognizing degrons, specific amino acid sequences sufficient to promote ubiquitination and degradation when embedded in a protein substrate. We hypothesized that degrons for the thalidomide-binding domain of CRBN could be installed on its substrates via post-translational modifications. Here, I will discuss our chemical biology approaches to discovering a degron for the thalidomide-binding domain of CRBN and its implications for the physiological function and therapeutic engagement of CRBN.
● 2025.10.29 澤田 知久 先生 講演会
日時: 2025年10月29日(水)16:00~17:30
場所: 理学部1号館4階 化学第1講義室(421室)
講師: 澤田 知久 先生
(東京科学大学総合研究院 化学生命科学研究所 准教授)
テーマ: 金属連結ペプチド鎖が織りなす新奇分子トポロジー
要旨: ユニークなトポロジーをもつ分子構造の化学合成は、40年間にわたり少しずつ進展してきたものの、複雑な絡まりトポロジーを実現する合成戦略は未だ乏しいのが現状である。本講演では、ペプチドのフォールディングと配位結合による自己組織化を協奏させるフォールディング集合法を用いることで、複雑な絡まりトポロジー構造の構築が可能であることを紹介する。金属連結ペプチド鎖によって構築されたトーラス結び目、多面体リンク、多面体空間グラフなどの実例について議論する。
● 2025.10.22 竹澤 浩気 先生 講演会
日時: 2025年10月22日(水)15:00~16:30
場所: 理学部1号館4階 化学第2講義室(414室)
講師: 竹澤 浩気 先生
(東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻 特任准教授)
テーマ: かご型錯体への閉じ込めによる分子操作:空間を活用した精密合成と中分子ホスト–ゲスト
要旨:
こちらからご覧ください。
● 2025.10.15 藤田 誠 先生 講演会
日時: 2025年10月15日(水)16:00~17:30
場所: 理学部1号館4階 化学第1講義室(421室)
講師: 藤田 誠 先生
(東京大学卓越教授)
テーマ: 化学と幾何学:自己組織化による巨大中空構造体の構築
● 2025.07.25 山口 尚登 先生 講演会
日時: 2025年07月25日(金)10:00~12:10
場所: 理学部1号館4階 化学第2講義室(414室)
講師: 山口 尚登 先生
(米国ロスアラモス国立研究所)
テーマ: 海外で研究者になるということ-アメリカで私が見たものを例として
● 2025.07.16 Victor Maurizot 先生 講演会
日時: 2025年07月16日(水)13:00-15:00
場所: 理学部1号館4階 化学第2講義室(414室)
講師: Dr. Victor Maurizot
(Institut Européen de Chimie et Biologie (IECB) CNRS researcher)
テーマ: Controlling the folding of aromatic oligoamide into well-defined 3D molecular architectures
要旨:
こちらからご覧ください。
● 2025.07.14 Mohamed S. H. Salem 先生 講演会
日時: 2025年07月14日(月)13:00-15:00
場所: 理学部1号館4階 化学第2講義室(414室)
講師: Dr. Mohamed S. H. Salem
(大阪大学 産業科学研究所 精密分子創製化学研究分野(滝澤研) 特任助教)
テーマ: Electrochemical Cascade Synthesis of Polycyclic Heteroaromatics: A Sustainable Gateway to Functional Optoelectronic and Photocatalytic Materials
要旨:
こちらからご覧ください。
● 2025.06.18 千葉 幸介 先生 講演会
日時: 2025年06月18日(水)13:20-14:50
場所: 理学部1号館4階 化学第2講義室(414室)
講師: 千葉 幸介 先生
(University of California, Berkeley HFSP Postdoctoral Fellow)
テーマ: 企業→社会人博士→海外留学と歩んだ私のキャリアパス
ポスター:
こちらからご覧ください。
● 2025.06.03 植村 卓史 先生 講演会
日時: 2025年06月03日(火)11:00~
場所: 理学部1号館1階 セミナー室(126室)
講師: 植村 卓史 先生
(東京大学 工学系研究科 応用化学専攻 教授)
テーマ: ナノ空間で高分子を制御する
● 2025.05.23 Catherine Gomez 先生 講演会
日時: 2025年05月23日(金)13:00~
場所: 理学部1号館1階 セミナー室(126室)
講師: Dr. Catherine Gomez
(Assistant Professor, Conservatory National of Arts and Grafts)
テーマ: Continuous Flow Synthesis of Metallic Nanoparticles and Their Applications
要旨:
こちらからご覧ください。
2024年
● 2024.09.17 Jun Wang 先生 講演会
日時: 2024年09月17日(火)15:00-17:00
場所: 理学部1号館4階 化学第1講義室(421室)
講師: Dr. Jun Wang
(Professor, Hong Kong Baptist University)
テーマ: Facile Access to Chiral Phosphorus Compounds via Transition Metal-catalyzed Asymmetric Hydrophosphination
要旨:
こちらからご覧ください。
● 2024.06.04 Bruno AMEDURI 先生 講演会
日時: 2024年06月04日(火)10:00-12:00
場所: 理学部1号館3階 化学演習室(318室)
講師: Dr. Bruno AMEDURI
(CNRS, Institut Charles Gerhardt)
テーマ: On the Overall situation of Poly- or Perfluoroalkyl substances (PFASs) including Fluoropolymers
要旨:
こちらからご覧ください。
● 2024.04.09 星本 陽一 先生 講演会
日時: 2024年4月9日(火)15:30-
場所: 理学部1号館4階 化学第1講義室(421室)
講師: 星本 陽一 先生
(大阪大学大学院工学研究科・准教授、附属フューチャーイノベーションセンター)
テーマ: 分子触媒の新手:フラストレーションを制御する機能の探求
要旨:
こちらからご覧ください。
● 2024.02.22 灰野 岳晴 先生 講演会

日時: 2024年02月22日(木)10:40-12:10
場所: 理学部1号館4階 化学第1講義室(421室)
講師: 灰野 岳晴 先生
(広島大学大学院先進理工系科学研究科・教授(副研究科長)、広島大学WPI-SKCM2 Principal Investigator)
テーマ: デザインされた分子認識が生み出す超分子ポリマーの機能化学
要旨:
こちらからご覧ください。
2023年
● 2023.10.20 南方 聖司 先生 講演会
日時: 2023年10月20日(金)10:30-12:00
場所: 国際交流プラザ3Fセミナー室
講師: 南方 聖司 先生
(大阪大学大学院工学研究科 応用科学専攻 物質機能化学講座 精密合成化学領域 教授)
テーマ: sp2およびsp3炭素のビシナル位官能基化
要旨: 我々は、sp2炭素で構成されている活性化されていない炭素-炭素二重結合のdiastereodivergentな触媒的ジアミノ化を見出している。本講演では、α,β-不飽和カルボニル化合物の触媒的なアンチ選択的ジアミノ化について述べる。また、窒素原子に電子求引基をもつ第2級アミン(主に環状第2級アミン)のαおよびβ位C(sp3)−Hのダブル官能基化反応(アミドハロゲン化)についても言及する。いずれもN,N-ジハロスルホンアミドを触媒あるいは反応剤とする遷移金属フリーな反応である。
● 2023.9.28 杉野目 道紀 先生 講演会

日時: 2023年9月28日(木)13:20-14:50
場所: 化学第1講義室(理学部1号館421室)
講師: 杉野目 道紀 先生
(京都大学大学院工学研究科 合成・生物化学専攻 教授)
テーマ: 小分子との動的相互作用を鍵とするらせん高分子のキラリティー制御と機能開拓
要旨: 溶液中で右巻きと左巻きの平衡にある「動的らせん高分子」のらせん方向を、溶媒やゲスト分子、温度や圧力によって高度に制御することができた。このらせんキラリティー制御に関わる分子メカニズムの最新の知見とともに、この高分子のキラリティー可換触媒・円偏光発光材料としての機能開拓について紹介する。
● 2023.6.13 笹野 裕介 先生 講演会
日時: 2023年6月13日(火)15:30-16:30
場所: 化学第1講義室(理学部1号館421室)
講師: 笹野 裕介 先生
(東北大学大学院薬学研究科 分子薬科学専攻 分子制御化学講座 合成制御化学分野 講師)
テーマ: ニトロキシルラジカル触媒を用いる酸化反応の新展開
要旨: ニトロキシルラジカルは、特異な酸化還元特性を有し、有機合成化学においてはアルコールの酸化触媒として重用されている。しかし、一般的なニトロキシルラジカル触媒的酸化反応条件を無保護のアミノアルコールに適用すると、一部基質の損壊が起こるのみであった。我々は、鋭意検討の結果、ニトロキシルラジカル/銅協同触媒によるアミノアルコールの化学選択的空気酸化反応と、ニトロキシルラジカル触媒による第三級アミンの空気酸化的脱アルキル化反応を見出した。本講演ではこれらの反応について詳細を述べる。
2022年
● 2022.12.15 生越 友樹 先生 講演会
日時: 2022年12月15日(水)13:00-15:00
場所: 化学第1講義室(理学部1号館421室)
講師: 生越 友樹 先生
(京都大学大学院工学研究科 合成・生物化学専攻 教授)
テーマ: 柱型環状分子ピラー[n]アレーンを基にした分子空間化学
要旨: 我々は、2008年にワンステップで簡単に合成が可能である柱型という新形状の環状ホスト分子「ピラー[n]アレーン」を見出した。本講演では、ピラー[n]アレーン発見の経緯から、ピラー[n]アレーンの形や反応性を利用した一次元チューブ構造の形成とその応用について、最近の成果について紹介する。
● 2022.9.14 LEQUEUX Thierry 先生 講演会
日時: 2022年9月14日(水)13:30-15:00
場所: 化学第1講義室(理学部1号館421室)
講師: LEQUEUX Thierry 先生
(Full Professor EXcept. class(Professeur des Universités, Prof PREX, CNU 32)
Université de Caen Normandie
Head of the Laboratory "Chimie Moléculaire et Thio-organique",UMR CNRS 6507 - ENSICAEN)
テーマ: Photocatalytic Amino(fluoro)alkylation of Alkenes
● 2022.7.27 澤田 敏樹 先生 講演会
日時: 2022年7月27日(水)15:00-16:30
場所: 化学第2講義室(理学部1号館414室)
講師: 澤田 敏樹 先生
(東京工業大学 物質理工学院 応用化学系 准教授)
テーマ: 生体系に着想を得た機能性ソフトマテリアルの創製
ポスター:
こちらからご覧ください。
● 2022.7.22 Dominique CAHARD 先生 講演会
日時: 2022年7月22日(金)15:00-17:00
場所: 化学第1講義室(理学部1号館421室)
講師: Dominique CAHARD 先生
(CNRS Research Director, UMR 6014 COBRA – Normandie Université)
テーマ: Assembly of fluorinated scaffolds with emphasis for asymmetric synthesis. Direct introduction of emerging fluorinated motifs versus Transformation of fluorinated building blocks.
要旨: The synthesis of enantiopure molecules featuring a fluorine atom or a fluorinated motif has stimulated considerable interest. The subtle effects of fluorine atom(s) on the course of asymmetric reactions often offer interesting results when compared with the chemistry of non-fluorinated molecules. The asymmetric construction of fluorinated molecules can be approached either by direct introduction of a fluorinated group or by transformation of prostereogenic fluorinated substrates. In this context, we have investigated various approaches which will be presented in the lecture.
● 2022.6.29 中嶋 裕子 先生 講演会
日時: 2022年6月29日(水)15:00-15:45
場所: 化学第2講義室(理学部1号館414室)
講師: 中嶋 裕子 先生
(名古屋大学 大学院理学研究科 物質理学専攻(化学系)生物有機化学研究室 研究員)
テーマ: 核酸の医薬への応用
要旨: 近年、核酸(DNA、RNA)を用いた医薬品の開発が急速に進められている。質量分析イメージング法を用いた核酸医薬品の薬物動態解析や、化学的な手法を用いたmRNA医薬研究を紹介する。
● 2022.3.4 叶 深 先生 講演会
日時: 2022年3月4日(金)15:00-16:30
場所: オンライン開催(聴講希望の方は近藤(
kondo.toshihiro2@ocha.ac.jp)までご連絡下さい)
講師: 叶 深 先生
(東北大学大学院理学研究科化学専攻 教授)
テーマ: 電気化学における種々の分光その場計測
要旨: 紫外・可視吸収分光、赤外吸収分光、ラマン分光、非線形分光などを電気化学系に適用した「その場測定」について、およびその適用例について紹介する。
● 2022.1.25 山崎 孝 先生 講演会
日時: 2022年1月25日(火)15:00-17:00
場所: 国際交流留学生プラザ 3F セミナー室
講師: 山崎 孝 先生
(東京農工大学 大学院工学研究院 応用化学部門 教授)
テーマ: p-キノンメチドを用いる含フッ素四級炭素骨格の構築
要旨: ペルフルオロアルキル基の中で最も頻繁に利用されるCF3基は、炭化水素であるi-Pr基とi-Bu基の中間の立体的嵩高さを示すことが知られている。そのため、この基を有する四級炭素骨格は医農薬品に散見されるものの、その構築には困難を伴うことが多い。我々は、用いる反応基質を適切にデザインすることにより、触媒量の塩基の使用でCF3基を含むp-キノンメチドを発生させることに成功した。さらに、この高反応性中間体は、様々な求核試薬と反応して望む構造を与えることが判明し、単なる四級炭素骨格だけではなく、四級炭素に連続する三級アルコール骨格の立体選択的調製にも成功したので、これらについて報告する。
2021年
● 2021.9.28 野田 秀俊 先生 講演会
日時: 2021年9月28日(火)13:00-14:30
場所: オンライン開催(聴講希望の方は三宅(miyake.ryosuke@ocha.ac.jp)までご連絡下さい)
講師: 野田 秀俊 先生
(公益財団法人 微生物化学研究会 微生物化学研究所 主任研究員)
テーマ: 高反応性活性種の制御に基づく飽和 N-ヘテロ環合成法の開発
要旨: 創薬化学におけるビルディングブロックとして多様な飽和 N-ヘテロ環の重要性が増しており、その新規合成法開発への期待が高まっている。我々は窒素遠隔位への官能基導入と窒素無保護のヘテロ環合成、という2つの特長を有する飽和 N-ヘテロ環の新規合成法の開発に取り組んでいる。特にβ-アミノ酸等価体として知られるイソキサゾリジン-5-オンを利用するレドックスニュートラルな分子変換に着目し、この複素環が金属触媒存在下アルキルナイトレン前駆体として振る舞うことを見出した。本講演では、生成したナイトレンの反応性を基質及び触媒により制御することで様々な骨格を有する環状β-アミノ酸が合成可能であることを示し、その背後にある反応機構に関し議論する予定である。
● 2021.7.28 佐藤 浩太郎 先生 講演会
日時: 2021年7月28日(水)13:20-15:00
場所: オンライン開催(聴講希望の方は矢島(yajima.tomoko@ocha.ac.jp)までご連絡下さい)
講師: 佐藤 浩太郎 先生
(東京工業大学 物質理工学院 応用化学系 教授)
テーマ: ビニルモノマーの精密重合と植物由来高分子への展開
要旨: 本講演では、我々がこれまでに開発してきた様々な新しい高分子合成手法および植物由来モノマーへの展開による新規バイオベースポリマーの開発に関する研究を紹介する。
● 2021.7.14 石毛 亮平 先生 講演会
日時: 2021年7月14日(水)13:20-15:00
場所: オンライン開催(聴講希望の方は矢島(yajima.tomoko@ocha.ac.jp)までご連絡下さい)
講師: 石毛 亮平 先生
(東京工業大学 物質理工学院 応用化学系応用化学コース 准教授)
テーマ: 機能性高分子の秩序構造と機能
要旨: 機能性高分子の高次構造と物性相関を主題として,特に含フッ素高分子,全芳香族ポリイミドの薄膜状態における秩序構造を放射光X線散乱法や新しい赤外吸収分光法で精密解析した事例をご紹介いたします。
● 2021.3.2 原野 幸治 先生 講演会
日時: 2021年3月2日(金)15:00-16:30
場所: オンライン開催(聴講希望の方は三宅(miyake.ryosuke@ocha.ac.jp)までご連絡下さい)
講師: 原野 幸治 先生
(東京大学総括プロジェクト機構 特任准教授)
テーマ: 分子のリアルタイム動画撮影でどんな化学が拓けるか?
要旨: 分子模型を見るがごとくに,有機分子のかたちと動きを観察したい」科学者の長年の夢である.近年の電子顕微鏡技術の進歩によりこの夢の実現に確実に近づいてきていたが,有機固体は電子線照射下で容易に分解するとされてきたことが電子顕微鏡の分子科学への応用を妨げてきた。我々は,カーボンナノチューブを担体として個々に担持した個々の有機分子は電子線照射下で十分に安定であることを見いだし,これを元に分子の振る舞いを原子分解能の動画として撮影する技術「Single-molecule atomic-resolution real-time electron microscopy(SMART-EM)イメージング」法を確立した。この手法により電顕観察の実時間スケールで一つ一つの分子が刻々と構造変換する様子を捉えることができ,さらには得られた単分子の動画を解析することで,一つの分子の中でどの部分が硬いか,柔らかいかという事まで目でみて調べることも可能である。さらには分子だけではなく,複数の分子が集まった集合体の動的挙動を観察すること,さらには数百個程度の分子を記録し統計的に処理することで,反応や運動が起こる機構を研究することも可能である。本講演ではこの新しい分析手法を用いた構造解析,分子運動解析そして化学反応研究の取り組みを紹介する。
2020年
● 2020.12.24 細井 晴子 先生 講演会
日時: 2020年12月24日(金)15:00-16:00
場所: オンライン開催(聴講希望の方は宮﨑(miyazaki.mitsuhiko@ocha.ac.jp)までご連絡下さい)
講師: 細井 晴子 先生
(東邦大学 理学部 生物分子科学科 准教授)
テーマ: 蛍光タンパク質の発光メカニズム
要旨: 蛍光タンパク質は生命現象のイメージング(生細胞観察)を可能にするレポータータンパク質として、生命科学分野の研究に欠かせないツールである。さまざまな性質や機能を持つ蛍光タンパク質が開発され、利用されている。これらの根幹をなすのが、蛍光タンパク質の発光メカニズムである。様々な蛍光タンパク質の発光メカニズムが調べられているが、現状では各論の域を脱していない。本講演では「なぜ蛍光タンパク質が光るのか」という基本的な問いに答えるため、超高速時間分解蛍光分光法により進めてきた研究を中心に発表する。
● 2020.02.20 Bruno AMEDURI 先生 講演会
日時: 2020年02月20日(木)15:00-17:00
場所: 理学部1号館4階 化学第二講義室(414室)
講師: Dr. Bruno AMEDURI
(Director, Institut Charles Gerhardt ; UMR (CNRS) 5253 – E.N.S. Chimie Montpellier)
テーマ: From Telomerization to Controlled Radical Polymerization of Vinylidene Fluoride and Applications Therefrom
要旨:
こちらからご覧ください。
2019年
● 2019.12.12 Lucile Fischer 先生 講演会
日時: 2019年12月12日(木)10:30-12:00
場所: 理学部3号館2階 会議室(209室)
講師: Dr. Lucile Fischer
(Chemistry and Biology of Membranes and Nanoobjects (CBMN, CNRS, Univ. Bordeaux))
テーマ: Aromatic oligoamide foldamer-based protein surface recognition
要旨:
こちらからご覧ください。
● 2019.11.01 内川 瑛美子 博士 講演会
日時: 2019年11月01日(金)16:00-17:30
場所: 理学部1号館4階 化学第二講義室(414室)
共催: リーディング大学院推進センター
講師: 内川 瑛美子 博士
(Research Scientist,
University of Texas Southwestern Medical Center, USA)
テーマ: cryo-EM structure reveals the activation mechanism of Insulin Receptor
クライオ電子顕微鏡を用いたインスリン受容体構造が解き明かす受容体活性化メカニズム
要旨: Activation mechanism of the insulin receptor revealed by cryo-EM structure of the fully liganded receptor–ligand complex
The insulin receptor (INSR) is a receptor tyrosine kinase (RTK) that plays essential roles in glucose metabolism. Dysregulation of IR signaling leads to metabolic syndromes, such as diabetes. Because of its therapeutic potential, INSR have been studied more than 50 years. Despite numerous amount of studies, the activation mechanism of INSR is only partially understood. The activation model where insulin bridges two INSR is generally accepted even if there is no structural evidence. Furthermore, the binding stoichiometry of insulin and INSR has not been determined. Biochemical studies indicated that insulin bind to two district binding sites on INSR by using two distinct interfaces but the second insulin binding site on the receptor remained elusive. Until now, the reported cryo-electron microscopy structures of INSR were unable to identify the location of the second binding site. Last year, we determined the high-resolution insulin bound INSR structure (3.1 Å resolution) using cryo-electron microscopy and finally identified the second insulin binding site. The complex configuration was different from the generally accepted bridging model. We determined four insulins in our structures and insulins does not bridge the INSR using two distinct interface. Insulins simply bind to the two binding sites using two interfaces. We proceeded to confirm the second binding site using mutagenesis and cell-based assays to confirm its significance. Our discovery provides a basis for understanding the activation kinetics of INSR and opens new research directions for the exploration of diabetes treatment.
● 2019.10.23 Mukund P. Sibi 先生 講演会
日時: 2019年10月23(水)16:00-17:30
場所: 理学部1号館4階 化学第一講義室(415室)
講師: Professor Mukund P. Sibi
(North Dakota State University, USA)
テーマ: Novel Templates for Synergistic Catalysis: Access to Congested Chiral Centers
要旨:
こちらからご覧ください。
● 2019.10.18 中西 陽子 先生 講演会
日時: 2019年10月18日(金)15:00-16:00
場所: 理学部1号館4階 化学第二講義室(414室)
講師: 中西 陽子 先生
(日本大学医学部病態病理学系腫瘍病理学分野 助教)
テーマ: 肺癌治療の変遷と薬剤耐性、そして糖鎖研究へ
要旨:
こちらからご覧ください。
● 2019.09.18 杉安 和憲 先生 講演会
日時: 2019年09月18日(水)17:00-18:30
場所: 理学部1号館4階 化学第一講義室(415室)
講師: 杉安 和憲 先生
(NIMS、九州大学 准教授)
テーマ: 超分子ポリマーの精密合成
要旨: 超分子化学と高分子化学の違いは何でしょうか?「超」と「高」、「Super」と「High」。なんとなく似ています。そしてこれら2つの化学の関連は?
2020年は高分子化学100年で、様々なイベントが企画されています。非常に興味深いことに、100年前に高分子の概念が提唱された時、実は、現在で言うところの「超分子ポリマー」のようなものがそれに対抗する概念として根強く信じられていました。クラウンエーテルが発見(1967年)され、その後、超分子化学にノーベル賞が与えられたのは1987年です。超分子ポリマーの研究が活発に行われるようになったのは、2000年以降のことです。
超分子か高分子か?一度は決着のついた論争でしたが、物性、機能、合成法など様々な点で、超分子ポリマーと既存の高分子の違いはあいまいにになってきています。本発表では、超分子ポリマーの合成法について最近の進展を紹介したいと思います。
● 2019.05.10 青木 誠 先生 講演会
日時: 2019年05月10日(金)10:40-12:10
場所: 理学部1号館4階 化学第二講義室(414室)
講師: 青木 誠 先生
(神戸大学大学院海事科学研究科 助教)
テーマ: 海事科学とは? -海を活用した研究-
要旨: 日本は四方を海に囲まれた海洋大国である。エネルギー問題や生活・環境の保全など世界規模の課題の解決に貢献し、自らの競争力を維持・強化するには、海洋の開発・活用・保全が不可欠である。神戸大学海事科学部は、大阪湾を望む深江キャンパスにあり、海や船をテーマとした教育・研究を行っている。本講演では、海洋を舞台とした海事科学部での研究、特に海洋再生可能エネルギーや海水資源など、海を活用した研究およびそれに関連する基礎研究について紹介する。
● 2019.01.11 Frédéric LEROUX 先生 講演会
日時: 2019年01月11日(金)10:00-
場所: 理学部1号館4階 化学第二講義室(414室)
講師: Dr. Frédéric R. LEROUX
(Director, University of Strasbourg, CNRS)
テーマ: Novel Methodologies towards Emergent Fluorinated Substituents
要旨:
こちらからご覧ください。
2018年
● 2018.12.12 Dominique Cahard 先生 講演会
日時: 2018年12月12日(水)10:00-
場所: 理学部1号館4階 化学第二講義室(414室)
講師: Dr. Dominique Cahard
(Directeur de Recherche CNRS,
UMR 6014 CNRS C.O.B.R.A. - Normandie Université)
テーマ: Fluorine & Chirality: Asymmetric Synthesis of Fluorinated Molecules
要旨:
こちらからご覧ください。
● 2018.11.01 Vincent ROBERT 先生 講演会
日時: 2018年11月01日(木)11:00-12:00
場所: 理学部1号館3階 309室
講師: Prof. Vincent ROBERT
(Strasbourg University, France)
テーマ: Variety of Orbitals for Electronic Structures Description
要旨: The concept of orbitals will be discussed starting from the earliest descriptions of bond formation. Localization-delocalization pictures will be used to describe different systems ruled by different Hamiltonians.
(参考)
Research activities:
ab initio calculations, phenomenological approaches, spectroscopic analysis, bistability magnetic systems, biomimestism, spin-crossover phenomenon, electron transfer and vibronic interactions
● 2018.10.31 Céline Olivier 先生 講演会

日時: 2018年10月31日(水)16:30-17:30
場所: 理学部1号館4階 化学第一講義室(415室)
講師: Dr. Céline Olivier
(Institute of Molecular Sciences, Université de Bordeaux–CNRS)
テーマ: Synthesis and Study of Organometallic Photosensitizers for Dye-Sensitized Solar Cells and Photo-Electrochemical Cells
要旨:
こちらからご覧ください。
● 2018.09.26 熊谷 直哉 先生 講演会
日時: 2018年09月26日(水)16:00-
場所: 理学部1号館4階 化学第一講義室(415室)
講師: 熊谷 直哉 先生
(微生物化学研究所 主席研究員)
テーマ: 特異ヘテロ環化合物の化学
要旨: 今までにない原子組成の分子骨格は新たな分子特性・機能を顕すことが多く、化学者を惹きつけてやまない。本講演では、いくつかの特異ヘテロ環化合物を紹介し、その分子の素性を議論していく。
● 2018.09.18 石井 洋一 先生 講演会
日時: 2018年09月18日(火)15:15-16:30
場所: 理学部1号館4階 化学第二講義室(414室)
講師: 石井 洋一 先生
(中央大学理工学部 教授)
テーマ: ビニリデン転位の一般化に向けて
要旨: 末端アルキンのビニリデン転位はよく知られており、合成反応にも広く応用されているが、内部アルキンは長い間この転位を行わないと誤解されていた。我々は、適切な配位子を持つ8族金属錯体を利用すれば、炭素置換基を2つ持つ内部アルキンといえどもビニリデンへの転位を行うことを見出し、その反応機構を鷹野研究室との共同研究で明らかにしてきた。そして、その結果として、利用できる金属元素も6族や9族へ、また転位させる置換基についても15・16族へと、高い一般性が見い出されつつある。本講演では、ビニリデン転位そのものの理解に向けた研究の流れと最近の展開を紹介する。
● 2018.09.11 市川 淳士 先生 講演会
日時: 2018年09月11日(火)16:00-
場所: 理学部1号館4階 化学第二講義室(414室)
講師: 市川 淳士 先生
(筑波大学数理物質系化学域 教授)
テーマ: フッ素脱離を基盤とする炭素-フッ素結合の活性化
要旨: 炭素-フッ素結合は、結合エネルギーの高さからその開裂による変換反応は困難とされ、その活性化には多くの場合、低原子価遷移金属による酸化的付加が利用されている。これに対して我々は、遷移金属種のより容易な素過程であるフッ素脱離に着目し、これによって炭素-フッ素結合の切断と新たな炭素-炭素結合の形成を同時に行えることを示してきた。本講演では、我々が取り組んでいるこうしたフルオロアルケン類の化学変換を紹介する。
● 2018.07.03 仙北 久典 先生 講演会
日時: 2018年07月03日(火)15:15-16:15
場所: 理学部1号館4階 化学第一講義室(415室)
講師: 仙北 久典 先生
(北海道大学大学院工学研究院 准教授)
テーマ: 二酸化炭素の電解固定化反応
要旨: 有機化合物の電解還元を二酸化炭素存在下に行うと、電解還元により発生したアニオン種が二酸化炭素を効率的に捕捉し相当するカルボン酸を得ることができる。本講演では、これまでに演者らの研究グループで展開してきた二酸化炭素の電解固定化反応について、その特長や一般的な化学的方法との比較等について様々な例を挙げて紹介する。
● 2018.05.17 Victor Maurizot 先生 講演会
日時: 2018年05月17日(木)15:00-16:00
場所: 理学部1号館4階 化学第一講義室(415室)
講師: Dr. Victor Maurizot
(CBMN, Université de Bordeaux–CNRS)
テーマ: Aromatic Oligoamide Foldamers: From Secondary to Quaternary Structures
要旨:
こちらからご覧ください。
2017年
● 2017.12.23 化学科主催研究会「お茶の水女子大学の理論化学と計算化学」
● 2017.12.22 若菜 裕一 先生 講演会
日時: 2017年12月22日(金)14:00-15:15
場所: 共通講義棟3号館1階 104室
協力: リーディング大学院推進センター
講師: 若菜 裕一 先生
(東京薬科⼤学 ⽣命科学部 分⼦細胞⽣物学研究室)
テーマ: 小胞体-ゴルジ体膜接触を介したタンパク質分泌制御
要旨: 脂質合成の場である小胞体は、様々なオルガネラとの間に脂質輸送・代謝に働く膜接触部位を形成している。小胞体-ゴルジ体接触部位では、小胞体膜タンパク質であるVAPやSac1がトランスゴルジネットワーク(TGN)膜上のCERTやOSBPとの結合を介し、セラミドとコレステロールをゴルジ体へと輸送する。しかし、この小胞体-ゴルジ体膜接触がゴルジ体機能に果たす役割はこれまでよくわかっていない。私たちは以前、TGNから細胞膜への構成性分泌経路を仲介する新規輸送小胞CARTS(carriers of the TGN to the cell surface)を同定し、TGNでのCARTS形成ならびにCARTS積み荷タンパク質ZG16B/PAUFのプロセシングに、上記の膜接触を介した脂質輸送が必要であることを報告した。本セミナーでは、その分⼦メカニズムに関する研究成果と膜接触部位新規構成因⼦の探索の試みについて紹介する。
● 2017.11.01 猪熊 泰英 先生 講演会
日時: 2017年11月01日(水)16:00-18:00
場所: 理学部1号館4階 化学第一講義室(415室)
講師: 猪熊 泰英 先生
(北海道大学 准教授)
テーマ: 結晶構造解析で何を見るか、何を知るか
要旨: 有機化学の研究において、単結晶X線構造解析は構造解析の中心的な役割を担ってきた。分子の立体構造のみならず、分子間相互作用や配向、巨大な超分子構造体の形成など結晶構造から得られる多くの情報は、溶液化学にも多大な貢献をし続けている。我々は、「結晶スポンジ法」と呼ばれる、液状のサンプルや微量化合物からでも構造解析用の単結晶試料を作製できる手法を開発し、様々な化合物の分子構造解析に成功してきた。また、近年では結晶構造を基盤として新しい分子を作り出し、その”かたち”を制御するという新しい展開にも着手している。本講演では、結晶構造解析を主体とした最近の研究成果を中心に紹介したい。
● 2017.07.07 小野 利和 先生 講演会
日時: 2017年07月07日(金)16:40-18:10
場所: 理学部1号館4階 化学第一講義室(415室)
講師: 小野 利和 先生
(九州大学助教、JST-さきがけ)
テーマ: 多成分系分子の自己組織化を利用した有機固体発光材料の創製
要旨: π共役分子の優れた光化学・電気化学特性を最大限に活かした高効率エネルギー変換材料は、次世代の光科学デバイス(波長変換材料、照明材料、有機EL材料等)創製において注目を集めている。しかしながら従来のデバイスの機能向上や機能発現に対するアプローチは、計算化学(分子設計)と有機合成技術に基づく手法に焦点が置かれており、「分子集積構造の制御」に注目した研究例は、その重要性にも関わらず、立ち後れているのが現状である。我々は、超分子化学と結晶工学の観点から“既知の有機化合物群”の集積化を通じて、新たな光機能性材料の創製を目的とし研究を進めている。
本研究では、π共役分子の集積化方法として、多孔性結晶空間への分子取り込み現象(包接現象)に着目した。一般的に嵩高い置換基を有する有機化合物(ホスト分子)は、それ自身は会合する事ができないが、溶媒分子(ゲスト分子)を取り込み結晶化することが知られている。 即ちホスト分子とゲスト分子の組み合わせを自在に共結晶化できる場であると考えられる。以上の概念「ヘテロ分子集積化技術」を基に、本発表では、①多色発光材料の創製、②白色発光材料の創製、③有機化合物センサーへの展開、④常温強リン光発光材料への創製、の4つのトピックに関して紹介する。
References:
T. Ono et al., J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 9519.
T. Ono et al., Chem. Eur. J., 2016, 22, 10346.
T. Ono et al., Chem. Lett., 2017, 46, 801.
● 2017.06.15 Tony Kung Ming SHING 先生 講演会
日時: 2017年06月15日(木)15:00-
場所: 理学部1号館4階 化学第一講義室(415室)
講師: Tony Kung Ming SHING 先生
(Department of Chemistry, The Chinese University of Hong Kong)
テーマ: Carbocyclization of Carbohydrates: Syntheses of Calistegines, Cocaine, and SGLT2 inhibitors
要旨: Carbohydrates, inexpensive and rich in stereochemistry, are Nature’s gifts to the synthetic organic chemists. Our research focuses on carbocyclization of sugars, i.e. the conversion of simple, readily available monosaccharides into hydroxylated carbocycles with pharmaceutical potential. Several key reactions will be presented in the seminar to illustrate such transformation namely intramolecular Watsworth-Emmon-Horner olefination and [π4s+π2s] cycloaddition, namely intramolecular nitrone-alkene cycloaddition. These protocols provide facile entries to 6 and 7-membered hydroxylated carbocycles in enantiomerically pure forms which then could be further elaborated into target molecules.
● 2017.06.10 桜化会OUCA主催 公開講演会(化学科共催)
日時: 2017年06月10日(土)13:40-15:45
場所: 理学部3号館701室(大講義室)
主催: 桜化会OUCA
【講演1 13:40-14:40】
講師: 岩田 茂美氏(平2化、平4院修)
(宇宙航空研究開発機構 有人技術部門 きぼう利用センター)
テーマ: 思いもかけなかった「宇宙」な仕事にたどり着くまで
要旨: 2年ほど前から関わっている国際宇宙ステーションでのタンパク結晶成長実験のプロジェクトを紹介するとともに、それまでの出来事を振り返ってお話ししたいと思います。これからキャリアを積んでいく皆さんへの応援メッセージになれば幸いです。
【講演2 14:45-15:45】
講師: 岩城 はるひ氏(平1化、平3院修、平11院博)
(資生堂グローバルイノベーションセンター)
テーマ: 太陽と上手に付き合うために…紫外線、サンケア商品の基礎知識…
要旨: 太陽光あふれる戸外での活動が気持ち良い季節になりました。地球上のいろいろな生物は太陽に大きな影響を受けながら暮らしており、人間もまた様々な恩恵を受けています。しかし近年では太陽光に含まれる紫外線の肌や健康への影響が取り上げられることが多くなってきました。そこで、紫外線とは、サンケア商品とは、どんなものかについてご紹介したいと思います。
※16:00-17:00 理学部3号館2階ラウンジにて茶話会を開きます。(無料)
⇒
桜化会OUCA
● 2017.05.09 小林 淳一 先生 講演会
日時: 2017年05月09日(火)13:30-
場所: 理学部1号館4階 化学第一講義室(415室)
講師: 小林 淳一 先生
(北海道大学名誉教授)
テーマ: 生物活性天然分子のケミカルバイロジー
要旨: これまで30数年にわたり、沖縄産の海洋生物(海綿、ホヤ、渦鞭毛藻、など)、陸上の植物(イチイ,ユズリハ、ヒカゲノカズラ、オトギリソウ、など)、海洋微生物(海洋細菌、海洋由来真菌、など)と陸上微生物(放線菌など)から、1000を超える新規生物活性天然物質(アルカロイド、マクロライド、ポリケタイド、テルペノイド、など)を単離、構造決定しており、これらの化合物の中には、新しい医薬品のリード化合物、あるいは生体機能解明のためのバイオプローブ(研究用試薬)として期待されるものが数多く含まれている。それらの中から代表的な研究例を紹介したい。
● 2017.04.03 内川 瑛美子 博士 講演会
日時: 2017年04月03日(月)10:00-11:00
場所: 理学部1号館4階 化学第一講義室(415室)
共催: リーディング大学院推進センター
講師: 内川 瑛美子 博士
(European Molecular Biology Laboratory (EMBL) ポスドク)
テーマ: 自然免疫におけるパターン認識受容体であるMDA5およびLGP2のX線結晶構造解析
要旨: 私たち生物はウィルスや菌などの非自己に感染されないように幾層もの防御システムを持っています。病原体が皮膚や粘膜といった一番身体の表面にある物理的なバリアーをくぐり抜け、細胞へと侵入すると、細胞の最初の防除システムであ自然免疫系が活動を開始します。自然免疫系のパターン認識受容体(PRRs)と呼ばれるタンパク質が非自己の特異的な特徴(PAMPs)を認識し、インターフェロンやサイトカインといったタンパク質を誘導し免疫応答経路を活性化させます。このPRRsが細胞内における最初のバリアーであり、細胞レベルでの病原体感染に対し防御に非常に重要な役割を果たしています。PRRsはこれまで多くの種類が報告されています。そのなかでもRig-I様受容体(RLHs)はインフルエンザウィルスなど多くのウィルスの核酸を特異的に認識します。RLHsにはRig-I、 MDA5、 LGP2 と三種類のタンパク質があり、それぞれその働きの違いが報告されています。Rig-Iについてはこれまで多くの研究が報告されていますが、特にLGP2についてはその構造の詳細な情報が少なく、LGP2はMDA5の働きに対し、正にも負にも働くことが示唆されていますがその詳細は十分にはわかっていません。今回、私たちは、LGP2とさまざまな2本鎖RNAとの複合体の結晶構造を高分解能で決定し、相互作用の詳細を明らかにしました。LGP2はRig-Iと比べ1 bp長い2本鎖RNAと結合しており、ATPの加水分解にともなうヘリカーゼドメインのコンフォメーションの変化がとらえられました。また、MDA5と10~27 bpの2本鎖RNAとの結晶構造を決定し、MDA5は短い2本鎖RNAに対しては、以前に報告された長い2本鎖RNAに対する配向とは異なる配向をとり結合することが明らかにされ、さらに、結晶構造をもとに作製した変異体を用いて、LGP2の2本鎖RNAとの結合がMDA5によるインターフェロンβの産生の誘導の亢進に重要であることが示されました。このことから、LGP2は2本鎖RNAとの結合により核を形成し、MDA5を線維状の重合体の形成へと導くことが示唆されました。
※講演会終了後、学生との交流会を開催します(化学第一演習室 422室)
● 2017.03.29 パデュー大学研究者(Chmielewski 先生、Hrycyna 先生)講演会
日時: 2017年03月29日(水)14:30-16:40
場所: 理学部1号館4階 化学第一講義室(415室)
共催: リーディング大学院推進センター
【講演1 14:30-15:30】
講師: Prof. Jean A. Chmielewski
(Alice Watson Kramer Distinguished Professor,
Department of Chemistry, Purdue University, USA)
テーマ: Peptides as Tools to Eradicate Intracellular Pathogenic Bacteria and Develop Biomaterials for Regenerative Medicine
要旨:
こちらからご覧ください。
【講演2 15:40-16:40】
講師: Prof. Christine A. Hrycyna
(Professor, Department of Chemistry, Purdue Univeristy, USA)
テーマ: Modulating ABC Transporters at Blood Brain Barrier
要旨:
こちらからご覧ください。
● 2017.02.16 Sylvette CHASSEROT-GOLAZ 先生 講演会
日時: 2017年02月16日(木)10:30-11:30
場所: 共通講義棟2号館 102室
共催: リーディング大学院推進センター
講師: Dr. Sylvette CHASSEROT-GOLAZ
(Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives,
CNRS UPR3212 - Université de Strasbourg)
テーマ: Implication of Annexin A2 in exocytotic site formation
要旨:
こちらからご覧ください。
● 2017.01.25 森田 明弘 先生 公開セミナー
日時: 2017年01月25日(水)15:00-16:30
講師: 森田 明弘 先生
(東北大学大学院理学研究科化学専攻 教授)
テーマ: 液体界面の分子科学
場所: 理学部1号館4階 化学第二講義室(414室)
要旨: 液体の界面の関わる現象は我々の身近にも多くの例をみることができ、界面化学、分析化学、電気化学などでの主要な対象となっている。しかし、界面での分子の振る舞いを正確に理解することは、未だに未開拓な問題が多く残されている。その大きな理由は、液体界面の分子を選択的に観測する実験手法が極めて乏しかったためであるといえる。数少ない有力な観測手法として和周波発生分光があり、我々はそれを分子シミュレーションによって解析する手法を国際的に初めて開拓してきた。実験と理論計算の共同で液体界面の現象が分子レベルで精密にわかるようになりつつある。セミナーではその成果をご紹介したい。
2016年
● 2016.11.02 Luis López-Remón 氏 講演会
日時: 2016年11月02日(水)12:45-13:30
場所: 理学部1号館4階 化学第一講義室(415室)
共催:リーディング大学院推進センター
講師: Luis López-Remón 氏
(ドイツLANXESS社 副社長)
演題: Overcoming the challenges to the chemical industry – the LANXESS example
講演会の後、13:30-14:20の予定で懇談会を行います。
● 2016.10.28 Michel Miesch 先生 講演会
日時: 2016年10月28日(金)16:00-17:00
講師: Michel Miesch 教授
(ストラスブール大学)
演題: Diastereo- and enantioselective routes to 14beta-hydroxyandrostane scaffolds
場所: 理学部1号館4階 化学第一講義室(415室)
● 2016.10.19 V. A. Soloshonok 先生 講演会
日時: 2016年10月19日(水)14:00-
講師: V. A. Soloshonok 教授
(バスク大学)
演題: The development of a new trifluoromethylation reagent and recent achievements of self-disproportionation of enantiomers
場所: 理学部1号館4階 化学第二講義室(414室)
● 2016.06.30 Ying-Duo Gao 先生 講演会
日時: 2016年 6月30日(木)15:00-16:30
講師: Dr. Ying-Duo Gao (高 穎多)
(Structural Chemistry, Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA)
演題: Computer-Aided Drug Design in Drug Discovery
場所: 理学部1号館4階 化学第一講義室(415室)
講演要旨: Computer-aided drug design has become an integral part of the drug discovery process. This talk will present two stories relaying general ideas on using structure-based design and computer modeling to accelerate the drug discovery process. The first story is about identifying potent and selective lead compounds for the NPY Y5 program in collaboration with Banyu Pharmaceuticals; the second one shows the use of structure-based design leading to the discovery of Omarigliptin, a DPP-4 inhibitor for the treatment of type II diabetes.
● 2016.02.12 大神田 淳子 先生 講演会

日時: 2016年02月12日(金)13:00-14:00
講師: 大神田 淳子 先生
(京都大学化学研究所)
演題: 細胞内たんぱく質間相互作用を制御する中分子の創製
場所: 理学部1号館4階 化学第一講義室(415室)
● 2016.02.05 加藤 隆史 先生 講演会
●2016.02.05 加藤 隆史 先生 講演会
日時: 2016年02月05日(金)16:40-17:40
講師: 加藤 隆史 先生
(東京大学大学院工学系研究科化学生命工学専攻)
演題: 自己組織化により機能材料をつくる
場所: 理学部1号館4階 化学第一講義室(415室)
⇒ 2015年―2006年の講演会記録
関連ファイル / Related Files
»  Abstract20240409Hoshimoto(PDF形式 397キロバイト)
Abstract20240409Hoshimoto(PDF形式 397キロバイト)
»  Abstract_20240604_Ameduri(PDF形式 657キロバイト)
Abstract_20240604_Ameduri(PDF形式 657キロバイト)
»  Abstract_20240917_Wang(PDF形式 659キロバイト)
Abstract_20240917_Wang(PDF形式 659キロバイト)
»  Abstract_CGomez_20250523(PDF形式 315キロバイト)
Abstract_CGomez_20250523(PDF形式 315キロバイト)
»  Mohamed_Abstract_20250714(PDF形式 740キロバイト)
Mohamed_Abstract_20250714(PDF形式 740キロバイト)
»  Abstract_250716_Maurizot(PDF形式 460キロバイト)
Abstract_250716_Maurizot(PDF形式 460キロバイト)
»  poster250618KosukeChiba(PDF形式 1,571キロバイト)
poster250618KosukeChiba(PDF形式 1,571キロバイト)
»  Abstract_251022_Takezawa(PDF形式 863キロバイト)
Abstract_251022_Takezawa(PDF形式 863キロバイト)
»  Abstract_sato_20260126(PDF形式 249キロバイト)
Abstract_sato_20260126(PDF形式 249キロバイト)
PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウインドウが開き、お茶の水女子大学のサイトを離れます)が必要です。
 Abstract20240409Hoshimoto(PDF形式 397キロバイト)
Abstract20240409Hoshimoto(PDF形式 397キロバイト) Abstract_20240604_Ameduri(PDF形式 657キロバイト)
Abstract_20240604_Ameduri(PDF形式 657キロバイト) Abstract_20240917_Wang(PDF形式 659キロバイト)
Abstract_20240917_Wang(PDF形式 659キロバイト) Abstract_CGomez_20250523(PDF形式 315キロバイト)
Abstract_CGomez_20250523(PDF形式 315キロバイト) Mohamed_Abstract_20250714(PDF形式 740キロバイト)
Mohamed_Abstract_20250714(PDF形式 740キロバイト) Abstract_250716_Maurizot(PDF形式 460キロバイト)
Abstract_250716_Maurizot(PDF形式 460キロバイト) poster250618KosukeChiba(PDF形式 1,571キロバイト)
poster250618KosukeChiba(PDF形式 1,571キロバイト) Abstract_251022_Takezawa(PDF形式 863キロバイト)
Abstract_251022_Takezawa(PDF形式 863キロバイト) Abstract_sato_20260126(PDF形式 249キロバイト)
Abstract_sato_20260126(PDF形式 249キロバイト)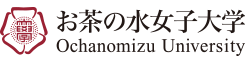


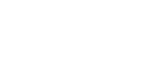
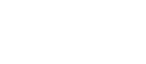
 日時: 2024年02月22日(木)10:40-12:10
日時: 2024年02月22日(木)10:40-12:10 日時: 2023年9月28日(木)13:20-14:50
日時: 2023年9月28日(木)13:20-14:50
 日時: 2016年02月12日(金)13:00-14:00
日時: 2016年02月12日(金)13:00-14:00